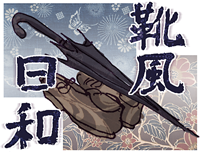
第01回 花を持てる女を求めて(その一)
―――― 向島から押上へ
―――― 向島から押上へ
文・カット/井上明久
荷風に都市散策の聖典とも言ふべき『日和下駄』と題する一代の名著あり。その真似の真似の真似にも遠く及ばねど、なほなにがしかの真似事をしたき思ひ抑へ難く、下駄の代りに靴をはき、フラリと町の風に吹かれ歩く。よつて、戯れに「靴風日和」と名付けたり。

地下鉄の浅草駅を地上にのぼると、むこうから何人ものほおずきを持った人が来る。そうか、今日はほおずき市か、ということは四万六千日だ。てことで、急遽、コースを変更して浅草寺に向かう。
仲見世はさすがにいつもにも増してごったがえしている。ようように本堂前にたどり着くと、本堂は修理中で残念ながらあの豪壮な瓦屋根を見ることはできない。一分ほどの時間に四万六千日分の祈りをこめてお参りをする。その後、当初の予定通り、吾妻橋を渡って向島に入ってゆく。
隅田公園に入りかけたあたりで、急にパラパラッと雨が降り出す。さして強くはないが濡れてすますほどではないので、折りたたみ傘を開く。やっぱり梅雨だ。雨の町歩きもそれはそれなりに別の風情があるのだが、ノートをしにくいのがちょいと困る。
公園の東側の植込みの中に、「堀辰雄住居跡」の案内板が建っている。無論、土地の人から「水戸さま」と呼ばれた水戸徳川家の下屋敷の内に堀辰雄が住んでいたわけではない。植込みの外側の道路をはさんだ真向かいにマンションがあり、もともとはその建物の前に案内板があったのだが、ある時からそれが取り払われ、どこかへ消えたのかと思っていたら公園内の植込みに移されていたというわけだ。
現住所で向島1‐7‐6、かつての新小梅町二番地に、父、実は養父の上条松吉と母の志氣(しげ)とともに、六歳の辰雄は引っ越してくる。明治四十三年の、九月頃か。
短篇『花を持てる女』は、「私はその日はじめて妻をつれて亡き母の墓まいりに往った」と言う書き出しで始まる。堀辰雄の母は、大正十二年九月の関東大震災の折り、隅田川に避難したが空しく水死した。その墓は父方の上条家代々の墓が建つ円通寺にある。寺は新小梅町の家から歩いていける距離だった。
「私たちのうちを出て、源森川に添ってしばらく往くと、やがて曳舟通りに出る。それからその掘割に添いながら、北に向うと」。
僕も堀夫妻と同じ道筋をたどりながら、円通寺に向かうことにする。隅田公園内の「堀辰雄住居跡」の案内板から離れ、源森橋のたもとに出る。弱い雨がまだ降りつづいている。源森橋の下を流れているのは北十間川だが、現在は隅田川まで貫通しているけれどかつては大横川の手前までしか開削されておらず、隅田川と大横川との間は別に源森川と呼ばれていた。
その、かつての源森川、現在の北十間川に沿って東へと歩き、小梅橋の横を左に曲がり、かつて曳舟川という掘割が流れていた現在の曳舟川通りを堀夫妻に倣って北に向かう。「右岸には大きな工場が立ち並び、左岸には低い汚い小家がぎっしりと詰まって、相対しながら掘割を挟んでいる」というのが、当時の、つまり昭和十三年頃の町並みだった。
とうの昔に右岸も左岸もなくなった。立ち並んでいた大きな工場は次々と外に出ていった。低い汚い小家はそこそこの高さの建物に変化した。堀夫妻が眺めた風景は今や片鱗もない。水が流れていたところに、ひっきりなしに自動車の往来があるばかりだ。
「地蔵橋という古い木の橋を私たちは渡って、向う側の狭い横町へはいって往った。すぐもうそこには左がわに飛木稲荷の枯れて葉を失った銀杏の古木が空にそびえ立っている。円通寺はその裏になっていて」。
大きな橋だと、川も橋もなくなっていても名前だけを今にとどめていることがあるが、古い木の橋だった地蔵橋の跡は何もない。ただ、その場所ははっきりとたどれる。向島4‐16から曳舟川通りを渡って押上2‐31に入っていく。そこに地蔵橋が架かっていたのだろう。
堀辰雄の文中には出てこないが左側にまず高木神社があり、その先の並びに飛木稲荷神社がある。飛んできた銀杏の枝が地にささり大木になったことから神社の名が付けられたというが、御神木の大銀杏の存在感はただただ凄い。周囲が少しばかり立て込んでいて充分に引きがとれないのが残念だが、それにしても圧倒される。人間は時間の前には頭を下げるしかないことを思い知らされる。
御神木をしばし見入っている間に雨があがる。円通寺は飛木稲荷のすぐ横手にある。「墓地は、道路よりも低くなっているので、気味わるく湿め湿めしていて、無縁らしい古い墓のまわりの水たまりになっているのさえ二三見られる位だった。/『ずいぶん汚い寺で驚いたか』私は妻のほうへふり返って言った」。
たしかに墓地へは数段降りてゆく。しかし、さっきまで降っていた雨のあとはほとんど残っていなかった。そして汚い寺どころか、むしろきれいすぎるぐらいにサッパリとしていて少し物足りない感じの今風の寺に変わっていた。本堂はコンクリート造りだが、瓦だけはなかなか風格があった。
墓の多くがまだ真新しい中を、「私の母の墓は、その二百坪ほどある墓地の東北隅に東に面して立っている」というのを頼りに上条の名を探すが見つからない。あるいは場所が移されたかととりあえず一巡してみるが、やはり見つからない。仕方なく、インターホンを押して寺の人にうかがうことにする。出てきた女性に、「こちらのお寺に、堀辰雄のお母さまのお墓があるとうかがったのですが」と言うと、いかにもすまなそうな表情をして、「ええ、昔はあったのですが今は……」と答える。「今はどちらにあるのかおわかりでしょうか」と重ねて訊くと、「いえ、わかりませんのですが……」との答え。
「私はその墓のまえにはじめて妻と二人して立った」というその墓は、そこにはなかった。新婚早々の堀辰雄と多恵子夫人がその前で頭を垂れた母の墓は、どこかへ消え去っていた。僕はなんだか中途半端な心定まらぬ思いを抱いたまま、陽射しがぶり返し始めた中、円通寺をあとにした。
源森川はその名を失い、曳舟川は暗渠となり、地蔵橋は姿を消し、堀辰雄の母の墓は円通寺からいずこかへ行った。ついでに加えれば、円通寺を越えた先には東武電車と京成電車のそれぞれの請地駅が相接するように並んでいたが、どちらの駅も今はない。ないないづくしの地上の変貌の中で、ただ堀辰雄の文学のみが変わらずに在る。