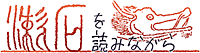
第02回 百年の昔から
文/井上明久

中で最も人口に膾炙しているのはスコットランドを舞台にした「昔」で、その書き出しは次の様である。
「ピトロクリの谷は秋の真下にある。十月の日が、目に入る野と林を暖かい色に染めた中に、人は寝たり起きたりしている。十月の日は静かな谷の空気を空の半途で包(くる)んで、じかには地にも落ちてこぬ。と言って、山向こうへ逃げても行かぬ。風のない村の上に、いつでも落ち付いて、じっと動かずに霞んでいる。」
間然として完全である。こんな文章を前にして、何を言おう。ただ、舌なめずりをするだけである。とりわけ、「秋の真下にある」の一語は、どうにも凄い。
ところで、本稿の主題はピトロクリの谷ではない。「昔」から三つ後ろに置かれた、つまり全二十五編の内の最後に近い二十三番目にある「心」という短章にある。文庫本で二頁半、四百字詰原稿用紙で五枚ほどのものである。このわずかな短さの中に、ある意味では漱石の最も重要な部分が秘められている。そう言っては、あるいは言いすぎかもしれない。けれど、そう言ってみたい。そんな想いが僕にはある。
まずはタイトルの「心」、というのが気になる。この短文を書いてから五年後の大正三年、漱石は長編小説『こころ』を執筆する。現在僕たちは、「上 先生と私」「中 両親と私」「下 先生と遺書」から成る『こころ』という作品を所有しているが、漱石がもともと抱いていた構想では、この『こころ』をも全体の一部とする、大長編小説『心』を予定していたという。
心とは、一般論から言っても人間にとって最重要な部分だが、漱石にとってはおそらく表現の中枢に据えるべき主題であり概念であったにちがいない。その「心」をこの短文の表題に与えている。となれば、なにがしか普通以上に漱石の思いが籠められている、そう思ってもいいのではないか。
さて、この短章「心」が、随筆なのか、小説なのか、それがよくわからぬ。どっちともとれる。あるいは、どっちでもいいのか。強いて言えば、『夢十夜』のどこかに紛れ込ませてもいいような、夢か、幻想か。
語り手は「自分」という一人称である。だから随筆ともとれるし、また小説であっても不思議はない。こんな書き出しだ。 「二階の手摺りに湯上がりの手拭を懸けて、日の目の多い春の町を見下すと、頭巾を被って、白い髭を疎らに生(はや)した下駄の歯入れが垣の外を通る。古い鼓を天秤棒に括り付けて、竹のへらでかんかんと敲くのだが、その音は頭の中でふと思い出した記憶のように、鋭いくせに、どこか気が抜けている。」
湯上がりの手拭を二階の手摺りにかけるというのは、旅先での旅館の光景だろうか。陽光がさす春の町、頭巾をかぶった下駄の歯入れ屋、竹のへらで鼓をたたくかんかんという音もどこか気が抜けて聞こえる。いかにものんびりとして穏やかな様子だ。ここには日常の持つ慌しさや切実感はない。どこか解き放たれたような、伸びやかな感じは、やはり旅先の気分に思える。それも、何となく温泉街でのような……。

「自分はその時丸味のある頭を上から眺めて、この鳥は……と思った。しかしこの鳥は……のあとはどうしても思い出せなかった。ただ心の底のほうにそのあとが潜んでいて、総体を薄く暈(ぼか)すようにみえた。」
この鳥は……、と来た。そう来たからには、当然何かある。『文鳥』を思い返せば、その何かはおのずと連想される。漱石をして鳥という存在が思い起こさせるもの……。が、旅の温泉宿でのこと、そう慌てて先を急ぐのも無粋である。
と書いたそばから、「自分はただちに籠の中に鳥を入れて、春の日影傾くまで眺めていた。」という文章を読むと、ちょっと慌ててしまう。旅館の部屋に鳥籠などあるだろうか。となると、これは語り手の自分の部屋での出来事なのだろうか。それにしても、ちょうど都合よく空の鳥籠がそこにあったりするものだろうか。もしも夢なら、もしも幻想なら、それでストンと胸に落ちはするのだが。
けれど、より大事なのは、それが事実か夢想かということではなく、自分はその鳥をただちに籠の中に入れた、と漱石が書いていることである。漱石を真似れば、「この籠は……と思った。しかしこの籠は……のあとはどうしても思い出せなかった。」とでもなろうか。
春の日が傾いた後、自分は散歩に出る。あてもなく、往来を右へ折れたり左へ曲がったりして、知らない人にあとからあとからすれちがいながら、どこまでも歩いてゆく。すると、風鈴が庇瓦に当たるような音がするので、その方を見ると、「五、六間先の小路(こうじ)の入口に一人の女が立っていた。」
まず、鳥が現われる。そして、鳥が女を呼び寄せる。この鳥は……、そうあの女を思わせる。いや、あの女の化身そのものである。
女の着物や髷は自分の記憶にない。自分の目に映ったのはその顔である。しかもその顔たるや――「目と口と鼻と眉と額といっしょになって、たった一つ自分のために作り上げられた顔である。百年の昔からここに立って、目も鼻も口もひとしく自分を待っていた顔である。百年ののちまで自分を従えてどこまでも行く顔である。」
たった一つ自分のためだけに作られ、百年前から自分だけを待ちつづけ、百年後まで自分を連れてゆく、顔。嗚呼、何という、顔だ。
『永日小品』中の一編「心」の語り手は、自分にとって運命そのものと思える顔を持つ女と、散歩の途次にこうして出逢うのである。果たして、この語り手は『永日小品』の作者なのか。つまりは、漱石という男はこういう女とこの世で現実に出逢ったのか。
おそらく、たぶん、そうなのであろう。それが、いつ、どこで、どういうふうに起こったか、はわからないが、「心」に描かれているような情景に漱石が全く無縁であった訳はないであろう。
女は小路の奥に入ってゆく。ふだんの自分なら躊躇するくらいに細くて薄暗い道を、身をすぼめるようにして後についてゆく。白い字を染め抜いた黒い暖簾がゆれている。軒燈が出ている。軒の下に更紗の小切れがかけてある。香水の瓶が見える。これって、何なのだろう。まるで遊廓みたい。あるいは、花街か。とにかく、素人の世界ではなさそうだ。ということは、この女は玄人なのか。
「露次は真黒な土蔵の壁で行き留まった。女は二尺ほど前にいた。と思うと、急に自分の方を振り返った。そうして急に右へ曲がった。その時自分の頭は突然さっきの鳥の心持ちに変化した。そうして女に尾(つ)いて、すぐ右へ曲がった。右へ曲がると、前よりも長い露次が、細く薄暗く、ずっと続いている。自分は女の黙って思惟するままに、この細く薄暗く、しかもずっと続いている露次の中を鳥のようにどこまでも跟(つ)いて行った。」
自分のためだけに作られ、百年前から待っていてくれ、百年後まで関わりを持つと信じられる顔をした女と出逢ったなら、そりゃあ、どういうところだって、どこまでだって、後を従いてゆくだろう。底知れぬ陶酔と言い知れぬ畏怖を抱きながら。
はじめ、二階の手摺り近くで小鳥を見た時、自分は鳥に女を見た。差し出した手にそっと飛び乗った鳥を、自分は籠の中に入れた。自分は春の日影が傾くまで、籠の中の女を飽かず眺めていた。
けれど、百年の女と出逢い、その後を追ってゆくうちに、自分の頭が鳥の心持ちに変化し、やがて鳥のようになってゆく。となると、籠の中にいる鳥は、女ではなく、自分なのかもしれない。