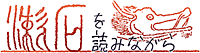
第10回 可哀そうな二人
文/井上明久

健三が、てことはつまりは漱石が、この御縫さんのモデルとなった女性を、ずっとあとあとまで気にかけていたように(と、勝手に僕が妄想しているだけなのだけれど)、僕も又、御縫さんのことが気にかかってならない。そう、僕は御縫さんにとても心惹かれているのだ。好きなのだ、まるで知らないくせして(どうも、惚れやすくっていけない)。
だから、『道草』の真ん中辺で、いきなり、「お縫さんが脊髄病なんだそうだ」という健三の言葉に、ひどく驚いてしまうのだ。そして、心が冷たくなってしまうのだ。
その時の健三とお住のやりとりは……
「可哀想ね今から脊髄病なんぞに罹っちゃ。まだ若いんでしょう」
「己より一つ上だって話したじゃないか」
「子供はあるの」
「何でも沢山あるような様子だ。幾人(いくたり)だか能く訊いて見ないが」
そして、自身がまもなくお産をしようとしているお住は、「成人しない多くの子供を後へ遺して死にに行く、まだ四十に充たない夫人の心持を想像に描い」てみたりする。
(因みに、どうでもいいようなことだが、前半では御縫さんだが、ここから後はお縫さんという表記になる。恐らくは長い連載中によくある、単なる表記上の不統一だと思うが、あるいは、悲劇性を帯びた女性への、せめてもの柔らかな労りの表現なのかもしれない。)
そして『道草』の後半で、そのお縫さんが亡くなる。それも、今や金をせびるためだけに健三のもとにやって来る、養父の島田の口を通して、それが告げられる。「お縫もとうとう亡くなってね。」
それは健三の同情を誘ったろう。健三の哀しみを深めたろう。そして、健三の心を暗くしたろう。けれど、お縫さんの死という事実以上に、健三が同情し、哀しみ、そして心を暗くしたのは、島田によってお縫さんの死が金の問題へとすぐさま転換されてしまうことであった。
お縫さんは、島田が後添えにしたお藤さんの連れ子であり、軍人の柴野と結婚した。島田によれば、「お縫が死んだんで、柴野とお藤の縁が切れちまったもんだから、もう今迄のように月々送らせる訳に行かなくなったんでね」ということになる。
島田にとってお縫さんの死は、血はつながっていないとはいえ、ある時期ともに暮らした娘の喪失ということよりも、より単純に、より端的に、金づるの喪失という意味しかなかった。
だから、「今迄は金鵄勲章の年金だけはちゃんちゃんと此方(こっち)へ来たんですがね。それが急に無くなると、丸で目的(あて)が外れる様な始末で、私も困るんです」という主張になり、結果、「兎に角斯うなっちゃ、お前を措いてもう外に世話をして貰う人は誰れもありやしない。だから何うかして呉れなくちゃ困る」という要求になる。
お縫さんの死が、島田をググッと健三に接近させる。それも情愛の面からではなく、ただ、金にしようという側面から。健三にしてみればその魂胆が気に食わず、「そう他(ひと)にのし懸って来たって仕方がありません。今の私にはそれ丈の事をしなければならない因縁も何もないんだから」と、突き返すしかない。

養父母は幼い健三を甘やかした。健三の望む玩具は何でも買ってあげた。けれど、それは純粋な愛情からではなかった。「夫婦の心の奥には健三に対する一種の不安が常に潜んでいた」。そしてその不安が、幼い子供に対して次のような残酷な質問を毎度重ねることになる。
「御前の御父さんは誰だい」
「じゃ御前の御母さんは」
「じゃ御前の本当の御父さんと御母さんは」
「御前は何処で生れたの」
「健坊、御前本当は誰の子なの、隠さずにそう御云い」
それらの質問にひとつひとつ、幼い健三は相手が一番気に入る答えを返しつづけねばならなかった。養父母の健三に対する愛には、無垢な自然がなかった。代りに、将来の見返りに対する粗雑な計算があった。法外な期待があった。そして、露骨な渇望があった。
そうした養父母の態度が、幼い健三に影響を与えぬわけはなかった。結果、「健三の気質も損われた。順良な彼の天性は次第に表面から落ち込んで行った。そうして其陥欠を補うものは強情の二字に外ならなかった。」
しかしながら、健三にとっての純一な愛情の不足は、何も養父母からだけではなかった。より深刻な不幸が、養父母の離婚によって戻されることになった実家で待ち受けていたのだ。
「実家の父に取っての健三は、小さな一個の邪魔者であった。何しに斯んな出来損いが舞い込んで来たかという顔付をした父は、殆ど子としての待遇を彼に与えなかった。今迄と打って変わった父の此態度が、生(うみ)の父に対する健三の愛情を、根こぎにして枯らしつくした。」
こうした大人たち(それも、養父母であり実の父である)に日夜接しなければならなかった健三の幼な心とは、如何ばかりであったろうか。ちょっと忖度しただけで、背筋を冷たいものが走る気がする。
「実父から見ても養父から見ても、彼は人間ではなかった。寧ろ物品であった。ただ、実父が我楽多(がらくた)として彼を取り扱ったのに対して、養父には今に何かの役に立てて遣ろうという目算がある丈だった。」
この冷徹な認識は、無論、『道草』を書いている四十八歳の漱石のものである。しかし、こうした認識につながってゆく痛切で深甚な思いを、十歳にも足らぬ子供が日々抱いていたことを考えると、余りにも苛烈であり、余りにも無残である。
このような体験をした子供が成長して大人になり、大学を卒業し、洋行をし、教壇に立つ身となる。つまり、明治期の合言葉である“立身出世”を遂げる。更には、小説も書き始めて文壇にも地位を築く。そうした健三に、四方から金を求める手が延びてくる。
世間的には高給取りと言える健三の家は、育ち盛りの子沢山のうえに、夫婦とも家計のやりくりが下手で出費が嵩み、常にきゅうきゅうとしている。それなのに、腹違いの姉には毎月きまって仕送りをしなければならない。最も盛んだった頃には五人の下女と二人の書生を抱える屋敷暮らしをしていた妻の実家が時勢の変化で没落し、そこにも恒常的な援助をしなければならない。時折り訪ねてくるようになった養母には、その度に「車へでも乗って御帰り下さい」と少なからぬ金を包んで渡さなければならない。そして、かつての義理を盾に金と交際を執拗に要求する養父と対峙しなければならない。無論その間、養父にはちょっとずつ金をむしり取られてゆく。 四方から攻められた健三は、「みんな金が欲しいのだ。そうして金より外には何にも欲しくないのだ」と考えざるを得なくて、「斯う考えて見ると、自分が今迄何をして来たのか解らなくなっ」てしまうのだ。
これが、『吾輩は猫である』を書いた後ぐらいの、三十七、八歳の漱石の姿と見ていいだろう。誰も自分をそうっと放っておいてくれない。誰もが自分をやたらと構いたがる。それも、「愛に駆られる衝動よりも、寧ろ慾に押し出される邪気が常に働いてい」るのだから、どうにも遣り切れない。漱石はそう感じ、胃を痛くしたのにちがいない。漱石はそう思い、頭を悪くしたのにちがいない。
唐突だが、お縫さんに戻る。冒頭に記したように、お縫さんは幼な子を何人か残し四十手前で哀れにも亡くなった。
漱石の、いや僕の妄想する二人の女の内のもうひとり、咲松(御作)の最期については、第8回の末尾で少しだけ触れたが、『硝子戸の中(ガラスどのうち)』からもうちょっと精しく見れば……
ある日、漱石は床屋に入る。初めて入る店だったが、亭主の顔にどうも見覚えがある。話しかけて見ると、昔、神楽坂肴町近くに店を持っていたという。姉の嫁ぎ先であり、漱石の従兄でもある高田を亭主はよく知っていた。
高田の家の真向かいにあった芸者置屋「東家」の話になり、漱石は亭主に「あすこに居た御作という女を知っているかね」と聞く。すると驚くことに、「知ってるどころか、ありゃ私の姪でさあ」と亭主は言う。漱石は心が動き、「それで、今何処にいるのかね」と重ねると、「御作は亡くなりましたよ、旦那」と亭主は答える。
動揺した漱石は、いつ、と尋ねることしかできない。「何時って、もう昔のことになりますよ。慥かあれが二十三の年でしたろう」と亭主は返し、「然(しか)も浦塩(ウラジオ)で亡くなったんです。旦那が領事館に関係のある人だったもんですから、彼地(あっち)へ一所に行きましてね。それから間もなくでした、死んだのは」とつづける。
漱石が、いや金之助が青春のとばくちで出会い、ほのかにふれあい、恐らくは金之助が一方的に心を揺らした二人の女性、お縫さん(れん)と咲松(御作)は、どちらも倖多い人生とは言えなかった気がする。思えば、可哀そうな二人である。そして本当は、漱石をも含めて可哀そうな三人と言うべきなのかもしれないが。