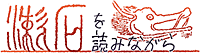
第08回 神楽坂と漱石
文/井上明久

五月十五日の土曜日、新宿歴史博物館で「神楽坂をめぐる作家たち」という題で話をした。矢田津世子、近松秋江、漱石の三人のことを話すつもりで用意をしていったのだが、寄道、脇道、廻り道に脚を取られて、津世子と秋江を話し終わったところで、約束の二時間をすでに十五分もオーバーしていた。そこで、はなから二人のことを話す予定であったかの如く振舞って話をまとめた。
本来ならその会場で話そうかと考えていたことを、だから、ここで書こうと思う。
喜久井町で生まれ、十代から二十代半ばまでをその地ですごし、そこからほど遠からぬ早稲田南町で晩年の十年を生きた漱石にとって、神楽坂という山の手きっての繁華街は、暮らしの場として、食事や寄席といった娯楽の場として、最も重要な空間であった。
そのことは、名品『硝子戸の中(ガラスどのうち)』で、極めて印象深く、そしてしみじみとした哀切感をともなって描き出されている。因みに、『硝子戸の中』に収められた三十九篇の文章は、大正四年の一月から二月に発表されたもので、翌五年の十二月に満四十九歳で亡くなることを思うと、後から取って付けた思い込みの謗(そし)りは免れないかもしれないが、ここでの漱石は淡々とした中に透徹と明澄を兼ね備えた、いわば「末期(まつご)の目」で書いているように思えてならない。
現在、東京メトロ東西線の早稲田駅を地上に出てすぐの所にある漱石生誕の地から神楽坂へと向かうその頃の様子が、こんなふうに書かれている。
「当時の私の家からまず町らしい町へ出ようとするには、どうしても人家のない茶畠とか、竹藪とか又は長い田圃路とかを通り抜けなければならなかった。買物らしい買物は大抵神楽坂まで出る例になっていたので、そうした必要に馴らされた私に、さした苦痛のある筈もなかったが、それでも矢来の坂を上って酒井様の火の見櫓を通り越して寺町へ出ようという、あの五六町の一筋道などになると、昼でも陰森として、大空が曇ったように始終薄暗かった。(略)
その位不便な所でも火事の虞(おそれ)はあったものと見えて、やっぱり町の曲り角に高い梯子(はしご)が立っていた。そうしてその上に古い半鐘も型の如く吊るしてあった。私はこうした有のままの昔をよく思い出す。その半鐘のすぐ下にあった小さな一膳飯屋もおのずと眼先に浮かんで来る。縄暖簾の隙間からあたたかそうな煮〆(にしめ)の香(におい)が煙(けぶり)と共に往来へ流れ出して、それが夕暮の靄に融け込んで行く趣なども忘れる事が出来ない。私が子規のまだ生きているうちに、『半鐘と並んで高き冬木哉』という句を作ったのは、実はこの半鐘の記念のためであった。」
引用が長くなった、などという常套句があるが、そんなのは糞くらえ、だ。漱石の文章なら、いくらだって引用したい。僕如きの文章などなるべくとっぱらって、出来れば漱石の引用だらけで構成したいくらいなのだから。実際、今引用した文の何とも言えない透明な美しさはどうだろう。そして、寂寥にも似た深い懐かしさはどうだろう。嗚呼! と短く声を挙げるしか僕にはない。
人家のない茶畠、竹藪、長い田圃路、火の見櫓、古い半鐘、小さな一膳飯屋、そして陰森とした五六町の一筋道……こんな風景が、今から百三十年ほど前の、喜久井町から神楽坂にかけての東京に広がっていたのだ。
今この辺りを歩いてみても、当時の縁(よすが)を偲べるものは何もない。パリならば、イタリアの町々ならば、百三十年くらい前の記憶の断片などゴロゴロ転がっているというのに。これが東京なのだ。それならいっそ、と負け惜しみから尻を捲くって言うことだが、なまじ碌でもないものが残っているよりも、漱石の文章、これさえあればいいのだ。
神楽坂には、漱石はより個人的な思い出を持っていた。神楽坂と大久保通りが交差する東南は神楽坂五丁目となったが、かつては肴町と呼ばれ、その一画に、漱石の従兄で、また異腹の姉ふさの夫でもあった高田庄吉が家を持っていた。そして、その高田の家の真向かいに東家という芸者屋があった。
「私はその東家をよく覚えていた。従兄の宅(うち)のつい向なので、両方のものが出入りの度に、顔を合わせさえすれば挨拶をし合う位の間柄であったから。」
高田の家には、漱石の二番目の兄や親戚の庄さんという者などが同居していて、通りかかる芸者に声をかけたり、家に誘ったりした。

漱石には賭博の才があったということか。あるいは、冷静な頭脳で相手の札を推理して勝ったということか。いずれにしろ、遊び人の兄たちや若い芸者たちに囲まれた少年金之助が、どんな表情や仕種をしていたか、想像がつくではないか。あばたを気にして俯き加減であったろう。大人たちの間で交される馴染みのない言葉や思わせぶりにとまどっていたであろう。あるいは、それと気づいて赤面もしたであろうか。激しく活動する内面の波瀾と、初々しいが野暮ったい外面の凡庸、この二つの狭間(はざま)に若き漱石の青春があった。
「一週間ほど経ってから、私は又こののらくらの兄に連れられて同じ宅へ遊びに行ったら、例の庄さんも居合わせて話が大分はずんだ。その時咲松という若い芸者が私の顔を見て、『またトランプをしましょう』と云った。私は小倉の袴を穿いて四角張っていたが、懐中には一銭の小遣さえ無かった。」
漱石が金がないからやらないと言うと、芸者は「好いわ、私が持ってるから」と応じる。明らかに、女の方が上手(うわて)を取っている。男は押されている。それでも観るべきものは観ている。そして、記憶している。
「この女はその時眼を病んででもいたのだろう、こういいいい、綺麗な襦袢の袖でしきりに薄赤くなった二重瞼(ふたえまぶち)を擦っていた。」
この咲松という若い芸者が、少年金之助に極めて忘れ難い思い出を刻み、また作家漱石になにがしかの文学的命題を植えつけたことは確かだろう。咲松から形づくられた女人像が、どう直接的に、あるいは変容の結果どう間接的に、作中のヒロインに投影されたのかは僕なぞには知りようもないが、そういうことが漱石のなかにあったのではないか、と思えてならない。
「その後私は『御作が好い御客に引かされた』という噂を、従兄の家で聞いた。従兄の家では、この女の事を咲松と云わないで、常に御作御作と呼んでいたのである。私はその話を聞いた時、心の内でもう御作に会う機会も来ないだろうと考えた。」
それから大分経って、友人と一緒に漱石が芝の観工場に行った時、そこでばったり御作に出会う偶然にぶつかる。
「此方(こちら)の書生姿に引き易えて、彼女はもう品の好い奥様に変わっていた。旦那というのも彼女の傍に付いていた。」
ちょっとした新派劇のワンシーンといったところではないか。御作と旦那は正式の夫婦なのだろうか。あるいは、御作は旦那の妾なのか。いずれにしても、書生の金之助からは遠い世界の住人ということになる。もともとが自分のものではないにもかかわらず、こういう時、人は深く遣る瀬ない喪失感を味わうものだ。若き漱石もこの時、現実における何かひとつのものの終わりを感じたにちがいない。そしてそれは後年、作品における何かひとつのものの始まりへと変貌していることを知ったにちがいない。
この話には哀れ深い後日談が続く。実は、初めて入った床屋の店主が偶然にも御作の叔父であったところから知ることになるのだが、御作はもうずっと昔、彼女が二十三の時に亡くなっていたのだ。それも、旦那に付いていったロシアのウラジオストックという見知らぬ遠い地で。青春の入口で淡く短くすれちがったひとりの女の、倖薄く波瀾に富んだ若き生涯に、漱石は深く想いを馳せたにちがいない。
この咲松(御作)が、『文鳥』の「昔し美しい女を知っていた。」の「美しい女」ではないかと、チラリと思ったりもする。紫の帯上げの房を長く垂らしたので女の細いくびすじを後ろから撫でまわしたり、座敷で仕事をしている女の顔に裏二階から手鏡で光を反射させて当てたりした、その相手がこの咲松ではなかったのか。
無論、妄想の域を出ない。けれど、僕にとってはそれで充分だ。