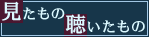2006年05月号 掲載
「坂の上の明治人」ノート
短期連載 第1回
四月十五日に、南海放送ラジオで、堀田建設スペシャル ひねもす~のたり“ラジオ放談”「坂の上の明治人」という二時間のラジオ生番組が放送された。今に汲むべき、明治という時代の美質、また明治人の魅力について、小説『坂の上の雲』と司馬遼太郎にふれながらパネリストたちが「炉辺談話」の雰囲気で語り合うという趣向であった。
パネリストは、かつての「中央公論」の名編集長として知られ、司馬遼太郎ともおつきあいのあった評論家の粕谷一希さん、そして、日露戦争をユニークな視点で描いた『動乱はわが掌中にあり』を書かれた作家で、元日本経済新聞論説主幹の水木楊さん、そして司馬遼太郎の『坂の上の雲』の三人の主人公たちの故郷松山から、「坂の上の雲」のまちづくりを推進中の中村時広松山市長の三人である。司会は南海放送の田中和彦アナウンサーと橋口裕子アナウンサー。
談話の自由闊達な雰囲気を伝えることはもとよりできないが、本号から何回かにわけて、パネリストの語られた内容を編集人がまとめたノートを掲載したい。今回は粕谷一希さんの第一回である。
パネリストは、かつての「中央公論」の名編集長として知られ、司馬遼太郎ともおつきあいのあった評論家の粕谷一希さん、そして、日露戦争をユニークな視点で描いた『動乱はわが掌中にあり』を書かれた作家で、元日本経済新聞論説主幹の水木楊さん、そして司馬遼太郎の『坂の上の雲』の三人の主人公たちの故郷松山から、「坂の上の雲」のまちづくりを推進中の中村時広松山市長の三人である。司会は南海放送の田中和彦アナウンサーと橋口裕子アナウンサー。
談話の自由闊達な雰囲気を伝えることはもとよりできないが、本号から何回かにわけて、パネリストの語られた内容を編集人がまとめたノートを掲載したい。今回は粕谷一希さんの第一回である。
粕谷一希さん 〈 第一回 〉
司馬さんについて
司馬さんとは司馬さんが直木賞をとった「梟の城」前後からのつきあい。司馬さんは、長編だけでなく中、短編にも傑作をたくさん書いた。「週刊中央公論」に「上方武士道」や「新選組血風録」を掲載し、中央公論社の編集者に司馬ファンが増えた。血風録は新選組ものの古典ともいうべき子母沢寛の「新選組始末記」をモデュファイし、近代的、合理的な主人公を造形をした。大宅壮一の企画で「近代日本の百人」の特集をした時は、宗教家の清沢満之(きよぎわまんし)について司馬さんに書いてもらった。産経新聞京都支局にいて寺廻りをしていたせいか、後には、『空海の風景』も書かれたが司馬さんは仏教と京都の仏教界に造詣が深かった。
司馬さんが明治という時代が好きだったのは、時代の近代的、合理的な雰囲気が資質にあったのではないか。司馬さんはいい主人公が見つけられないと筆が進まない人だったと思う。昭和が嫌いというのは、書きたい主人公がいなかったということ。
「坂の上の雲」は身を立て世に出るという「立身出世」が若者みんなのスローガンとしてあった、明るく爽やかな明治という時代と主人公を描いた。司馬さん本人も実に爽やかで魅力的な人。話し好きな人で、会うと、二時間、三時間離さない。話に花があって、聞いているこちらも気分が昂揚した。酒は、「書生酒」で議論を楽しむ酒だった。
日露戦争、明治と昭和のちがい
日露戦争のあざやかな勝ち方、成功が後の失敗の原因になった。勝利が反省の声をかき消してしまった。具体的には日露戦争の勝利で得た満鉄の権益が関東軍の肥大化と軍の暴走につながったというのが僕の仮説。戦争が悪いのは当たり前だが、明治は主権国家が絶対、国が滅びれば民族が滅びる時代だった。国が個人の安全を守る最後の単位だった。太平洋戦争後、原爆が主権国家の絶対性を無意味化した現代と明治の主権国家の時代は違う。実際、第二次大戦後は朝鮮戦争でもベトナム戦争でも宣戦布告をした国家同士の戦争はなかった。戦後の人間が戦争を否定するのは無理もないが、国家の役割が変わった現代と明治とを同一視するのは歴史を等閑しているというしかない。司馬さんからは、戦後の日本は日本人のエネルギーが開放されたという点で、日本のルネッサンス、光悦らが出て、絢爛たる芸術が花開いた安土桃山時代とよく似ていると直に聞いた。一面、当たってはいるが、アクセントの置きかたで変わる部分もある。昭和は、軍人が威張り出し、国家の仕組みが悪くなって、悲劇的な時代だったかもしれないが、昭和の軍人にも声高に語らず誠実に生きたすぐれた人もいた。
『日本のいちばん長い日』の阿南惟幾大将や、知英派でもともと開戦に反対していながらフィリッピンで処刑された本間雅晴中将、軍縮派で開戦に反対した山梨勝之進、堀悌吉らもいたということを、同時代を生きたものとして言っておきたい。成功が失敗の原因になる。不断にもとの意味を問い直すことが必要だ。そうしなければ、いつの時代でも、目的と手段の逆転現象が起きる。
国家と公(おおやけ)について
五箇条の御誓文が「万機公論に決すべし」と言い、又教育勅語に「一旦緩急あれば義勇公に奉じ」とある。国ではなく公と言っている。国家は公を含み公を実現するから大事なものだった。明治の国家とはそういうものだった。付言すると、公を論じ、公のために生きるというのは明治の日本人だけではない。アメリカのウォルター・リップマンの『世論』(掛川トミ子訳 岩波文庫)は『パブリック・オピニオン』で「公論」と訳すのが至当。そのリップマンに『公共の哲学(パブリック・フィロゾフイー)』(The Public Philosophy, (Hamilton,1955).(矢部貞治訳『公共の哲学』時事通信社、一九五七年)という感動的な本がある。彼はその中で「「公共というのは選挙における多数、世論調査における多数ではない。かつて生きた祖先達、これから生まれてくるであろう子孫達を含めたものが公」ということを言っている。環境問題も後の世を視野にいれなければお話にならない。
今は、「私」の時代の極致で他人との関係をいやがる消極的な子供もいる。地球人類を考えれば、国家も「私」と言える。国家を否定する人類主義者や、平和主義者がいるが、現実的に言えば、二十一世紀も国家が基礎的な単位であることはかわらない。新しい時代をつくると、格好のいいことを言うよりも、自分がどこまでやれるか。どこまでやるかが大切だと思う。人のことを言っても仕方がない。
●次回は粕谷さんの第二回。粕谷さんの好きな明治人、松山についてなどを掲載します
文責/編集人


粕谷一希さん / 水木楊さん
粕谷一希さん
1930年生まれ。東京大学法学部卒業後、中央公論入社。「中央公論」「歴史と人物」などの編集長。同社退社後、雑誌『東京人』編集長を経て、ジャパン・ジャーナル代表取締役社長。
評論家、文筆家。『二十歳にして心朽ちたり』、『戦後思潮』、『対比列伝』など著書多数。
1930年生まれ。東京大学法学部卒業後、中央公論入社。「中央公論」「歴史と人物」などの編集長。同社退社後、雑誌『東京人』編集長を経て、ジャパン・ジャーナル代表取締役社長。
評論家、文筆家。『二十歳にして心朽ちたり』、『戦後思潮』、『対比列伝』など著書多数。
Copyright (C) TAKASHI NINOMIYA. All Rights Reserved.
1996-2012