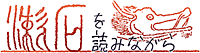
第04回 太平な、男ふたり女ひとり
文/井上明久

それにしても『一夜』、何とも摩訶不思議、奇妙奇天烈、面妖怪々然の代物で、つまり平たく言ってしまえば、僕には珍紛漢紛の、謎だらけの作品なのである。
発表当時、その種の評があったかどうかは知らないが、漱石自身、『吾輩は猫である』の「六」で、東風君の口を借りてこんな戯文を書いている。
「せんだっても私の友人で送籍という男が一夜という短篇を書きましたが、だれが読んでも朦朧として取りとめがつかないので、当人に逢ってとくと主意のあるところを糺してみたのですが、当人もそんなことは知らないよと言って取り合わないのです。」
なるほど、朦朧、ね。たしかに、この作品に一番似つかわしいのは、「朦朧」の一語、かもしれない。
季節とか時間とか場の設定とか人物の外貌など、外なる世界はいたって明瞭だ。けれど、彼らの関係とか思惑といった内なる世界が、甚だ朦朧なのである。
タイトル通りの文字通り、「一夜」の話である。五月雨が降っている。蚊遣の煙が揺れている八畳の座敷に人が三人いる。三人の内訳は、男がふたりに女がひとり。これが登場人物のすべてで、誰にも名前が与えられていない。
男のひとりは髯ある人で、床柱にもたれつつ膝頭を両手に抱いて、「美しき多くの人の、美しき多くの夢を……」と吟じている。もうひとりの男は五分刈をして髯を貯えぬ丸顔で、縁側にあぐらをかいて、「描けども、描けども、夢なれば、描けども、成りがたし」と誦している。女は白地の浴衣で涼しき目をして、「画家ならば絵にもしましょ。女ならば絹を枠に張って、縫いとりましょ」と言う。

髯ある男が「美しき多くの人の、美しき多くの夢を……」と再び吟ずると、「縫いにやとらん。縫いとらば誰に贈らん。贈らん誰に」と女が加える。すると、髯なき男が「我に贈れ」と言い添えてカラカラと笑う。髯は「縫えばどんな色で」と真面目に訊く。「絹買えば白き絹、糸買えば銀の糸、金の糸、消えなんとする虹の糸、夜と昼との界(さかい)なる夕暮の糸、恋の色、恨みの色は無論ありましょ」と女は眼をあげて床柱の方を見る。
となると、女は髯なき男よりも髯ある男の方に、より想いが傾けられていることになるのか、どうか。髯あるは冷静かつ性情ややつれなく、髯なきは闊達かつ直朴なる性格なのか、どうか。ただそんな風に思ってみるだけで、言い切れそうにない。
ところで、女が髯の男に最初に答えた時の描写はこうだ。「朱塗の団扇(うちわ)の柄(え)にて、乱れかかる頬の黒髪をうるさしとばかり払えば、柄の先につけたる紫のふさが波を打って、緑り濃き香油の中に躍り入る」。そして二度目に答えた時はこうだ。「愁(うれい)を溶いて練り上げし珠(たま)の、烈しき火には堪えぬほどに涼しい。愁の色は昔しから黒である」。これは、『草枕』の那美さん、『虞美人草』の藤尾、の原型ではないか。
夜のしじまの中で、ほととぎすがククーと鳴く。少しおいて、ククー、ククーと鳴く。髯男は生まれて初めて聞いたとみえ、「一声でほととぎすだと覚る。二声で好い声だと思うた」と言うと、「ひと目見てすぐに惚れるのも、そんな事でしょか」と女が問う。五分刈は「あの声は胸がすくよだが、惚れたら胸は痞(つか)えるだろ。惚れぬ事。惚れぬ事……」と言う。
さっきの三人の会話よりも、ここでのやりとりは一歩先へ、もう少し現実寄りへと進んでいる感がある。惚れるという言葉があからさまに出てくる。それも、女の口から。そこで男のひとりが、惚れることの実際的な剣呑さを暗示して、惚れぬ事よとサラリと逃げる。
さてこの後、この三人に、何が起きる、というほどのこともない。髯ある男が始めようとする夢語りは、蚊遣火が消える、一匹の蜘蛛が出てくる、二疋の蟻が這い出す、そんなこんなで中断される。
やがて、「夜もだいぶ更けた」「ほととぎすも鳴かぬ」「寝ましょか」、と短い台詞が三つ重ねられ、それにこう文章が続く。「夢の話しはついに中途で流れた。三人は思い思いに臥床(ふしど)に入る。」
三人が語らっていたのは八畳の座敷である。これって、八畳間に三人で雑魚寝をしたってことなのか。それとも、ここは旅館か何かの一室で、あとの二人はそれぞれ自室に戻って寝たということなのか。ま、仮に八畳に三人が寝たとしても、この三人の間からは肉体的な事柄は限りなく起きそうにない。三人はそういう部分を巧妙に擦り抜けたところに、少なくとも、今はいる。だからこそ、三十分後に寝入った三人を表して、漱石は「彼らはますます太平である」と言う。
こうして三人の一夜は終わる。けれど、この短くて、朦朧としていて、取りとめのない『一夜』という小説はこれで終わることなく、その後の漱石作品の原型となっていったのではないか、と僕は思っている。
『一夜』の三人は、『一夜』の男ふたりと女ひとりは、聖三角形(セント・トライアングル)の関係を保っている。ここにはまだ肉の匂いはない。罪への誘いもない。だから、太平なのである。そうした太平な聖三角形(セント・トライアングル)が、やがて、壊れてゆく。それが漱石の作品世界の通奏低音である。
淡い形ではあるが『虞美人草』『三四郎』がそうである。『彼岸過迄』『行人』にもその影がある。『それから』『門』『こころ』はまさにそのものである。漱石は、男ふたり女ひとりの関係に拘った。拘りつづけた。
その祖形が『一夜』にある。『一夜』の男ふたり女ひとりには名前が与えられていない。であるからこそ、重要なのである。つまりこの三人は、やがて、代助と平岡と三千代とも、宗助と安井とお米とも、先生とKとお嬢さんとも、誰にでもなり得るのだ。
まだ肉の匂いもなく、罪への誘いもない、太平な、聖三角形(セント・トライアングル)の男ふたり女ひとりの関係を漱石が描いたのは、『一夜』、これ一回きりである。あるいは、ここに漱石の理想が、見果てぬ夢があったのかもしれない。しかし、現実はそのままでは終わらない。『こころ』の先生が言うように、「恋は罪悪ですよ」という地点まで行かねば済まない。